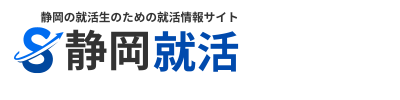大学生活を謳歌していると、気づくと就職活動の時期になっており、ガクチカとして話せる内容がなくて困るというのはよくある話です。特に、昨今コロナウイルスの蔓延により活動が制限された結果、面接時に話せる学生時代に力を入れて取り組んだこと(以下、ガクチカ)がないという学生も多いです。この記事では、ガクチカがなくて困っている学生に、あまり時間をかけずに作れるガクチカやガクチカがない場合の対策、選考突破方法について詳しく解説します。
ガクチカがない場合に選考を突破するためのポイント
まずは、ガクチカがない場合に、ガクチカ以外のポイントで勝負する戦略をお伝えします。選考方法やアピールの仕方を工夫することで、ガクチカ以外の場所で選考突破を目指しましょう。
大学以前のポートフォリオや実績
大学時代に力を入れたことはなくても、部活等、中学高校時代であれば話せるガクチカがあるという方もいらっしゃると思います。そのような方は、中学高校の頃の話を中心に語り大学時代は学業に専念したいと考えて、専念していたという構成にするのも1つの戦略です。
ポートフォリオとは、過去の作品や実績をまとめた資料のことで、実際に企業に提出するのもいいですが、大学以前からの自分の活動をまとめるのに使えるので、ぜひ作ってみましょう。実績を具体的な数値や事例で示すことで話のわかりやすさが上がるため、効果的に自分の能力や独自性をアピールできるよう用意をしましょう。
自己紹介動画の提出
こちらは、ガクチカ等を記入するエントリーシート(ES)のみで選考する企業や採用ルートを避け、自己紹介動画などの提出を求める、やや面倒くさい選考方法を選ぶという戦略です。自己紹介動画では、自分の経歴やスキルを短時間で伝えることが求められますが、動画の内容はガクチカではない場合が多いです。
明確な構成と簡潔な表現を心がけることで、顔が見える方法である分、話し方や表情などのポイントで評価を得られる可能性があります。背景や音声も注意して、プロフェッショナルな印象を与えるように心がけてください。
オンラインテストや適性検査の利用
こちらも、ESのみの選考を避ける戦略の1つですが、地頭の良さや論理的思考力をアピールすることができます。得意な人であれば、高得点を取ることで、ガクチカの弱さを克服することができます。
オンラインテストや適性検査を受ける際は、集中力や時間管理が重要です。適切な環境で受験し、事前にテスト範囲を把握しておくことが大切です。入念な準備をして、ライバルと差をつけましょう。
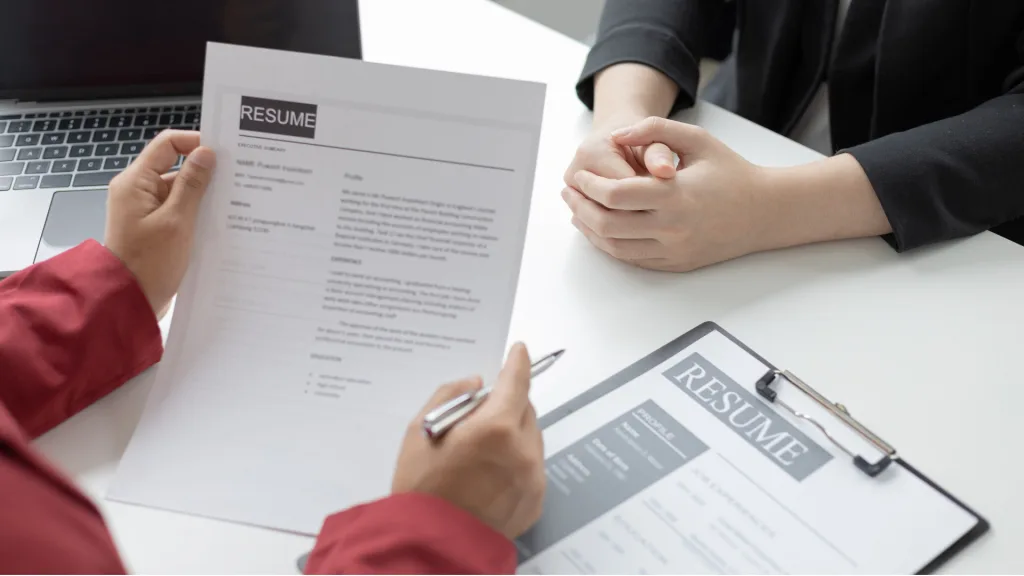
グループディスカッションやプレゼンテーション選考
グループディスカッションを序盤の選考で課す企業もあります。グループディスカッションでは、意見交換や議論を通じて、チームワークの中でのコミュニケーション能力やプレゼンテーションでのスピーチ力などをアピールすることができます。
相手の意見を尊重し、建設的な意見を提案することを意識しながら、プレゼンテーションでは、内容の構成やビジュアル表現に工夫を凝らすことで、効果的に評価を受けることができます。また、質疑応答にも丁寧に対応し、自分の考えを明確に伝えてあなたの魅力を伝えていきましょう。
続いて、そもそもガクチカを使わない採用ルートを目指す方法について述べます。
インターンシップや企業主催プロジェクトに参加
インターンシップに参加することで、インターン参加者用の特別選考ルートで選考を受けることもできます。特別ルートでは、主にガクチカについて問われる1次選考などの初期選考を飛ばして選考を進めることができます。
また、早期のインターンシップや企業主催のプロジェクトへの参加は、実務経験を積む絶好の機会で、それ自体をガクチカにしている人もいます。主体的に取り組み、企業との相性を確かめつつ、インターンシップの成果や学びを選考に活かしましょう。
ネットワーキングイベントや業界セミナーへの参加
企業主催のネットワーキングイベントや業界セミナーに参加することで、企業や業界の最新情報やコネクションを直接得ることができます。企業関係者との交流によって、自分のアピールや人脈形成に繋がり、繋がった社員から、ガクチカだけでない魅力を推してくれるケースもあります。積極的な参加とコミュニケーションを心がけ、対人能力も鍛えながら人脈と企業理解を深めましょう。

短期間で作れるガクチカ
本選考までに、まだ時間がある方は、短期間で作れるガクチカを試すのも戦略の1つです。ただ、注意が必要なのは、短期間でガクチカを作る場合、大学一年生から意識高く行動しているライバルが4〜6年間かけて学んだ内容を、一ヶ月で習得する必要があるということです。これは、かなりハードルが高く、決して楽ではありませんし、ジャンルも絞らなければ中途半端に終わる可能性も高いです。
そのため、モチベーションに不安がある方は、業界理解・企業理解などの他の部分を強くする方が良い場合もあるため、よく考えて覚悟を決めてから取り組みましょう。
一ヶ月で作れるガクチカのテーマ
1.オンラインコースやセミナーを受講
一ヶ月以内で学べるオンラインコースやセミナーを受講し、新しいスキルや知識を習得しましょう。これにより、自己成長や興味関心の証明として面接でアピールできます。一ヶ月のうちに複数のセミナーやオンラインコースを受講して、4年分に匹敵するような受講実績を作りましょう。
なお、この際に、就活セミナー等に参加する方がいますが、就活セミナー等はほとんどの学生が参加するものであるため、自分の興味に近い、なるべくニッチなジャンルを選ぶことをお勧めします。
2.インターンシップやボランティア活動
短期間のインターンシップやボランティア活動に参加し、実務経験を積むことができます。これらの活動はチームワークやコミュニケーション能力、問題解決能力などを磨く絶好の機会です。
3.自主プロジェクトの立ち上げ
ブログや起業、イベント、サービス開発など、ほとんどの大学生が経験していない経験をすることで、4年間分の行動を取り返せるチャンスがあります。自分の興味や関心に基づいた小さなプロジェクトを立ち上げ、真剣に取り組むことで、たとえ1ヶ月であっても、面接で誇れる経験になります。例えば、ブログを書いたり、SNSで情報発信をしたり、オンラインで勉強会を企画するなど、自分のアイデアやスキルを活かしながらプロジェクトを遂行してみましょう。
4.読書や映画鑑賞を通じた学び
大学生の読書の平均時間は一ヶ月あたり30分程度とされています。また、全く読まない大学生も全体の46%ほどであるため、大学生の4年分の読書を一ヶ月で行うことが可能です。そのため、ガクチカがない就活生でも、読書を武器にすることも可能なジャンルだと言えます。
読書や映画鑑賞を通じて得た学びや気づきを、面接で話題にすることができ、特に、自分の業界や職種に関連する本や映画を選ぶと、面接官に自分の興味や熱意をアピールできます。
5.言語学習や資格取得の取り組み
一ヶ月で目に見える成果を出すことは難しいかもしれませんが、言語学習や資格取得への取り組みを始めることができます。継続的に努力している様子を面接で伝えることで、自己成長への意欲や向上心をアピールできます。
これらの経験は、一ヶ月以内で完了し、面接で話すことができる内容です。自分の興味や行きたい企業に合った方法を選び、効果的にアピールできる経験を積んでください。

半年間で作れるガクチカのテーマ
こちらは、3年生の夏のインターン選考で失敗した方や、冬のインターン前で不安がある方、ガクチカがなくて就職留年してしまった方など、比較的時間がある場合に作れるオススメのガクチカのテーマです。目安として半年間にしましたが、短くても長くても取り組み方の姿勢によって、学べる事の量も質も変わるため、期間は多少前後しても、真摯な姿勢で取り組みましょう。
1.長期インターンシップ
半年間の長期インターンシップを経験することで、業界や企業に関する深い知識や実務経験を積むことができます。実務を経験できるため、取り組み方によっては半年間でも、社会人顔負けの経験を積むことも可能です。面接では、インターンシップでの成果や学びをアピールできるため、なるべく裁量の大きな、チャレンジングな環境に身を置きましょう。
2.ボランティアプロジェクトへの参加
社会貢献性の高い企業などに関心がある場合は、半年間のボランティアプロジェクトに参加し、地域貢献や社会貢献活動を行うことがお勧めです。大学生が参加したことのあるボランティアは数日や長くても1週間程度であることがほとんどであるため、長期に渡るボランティアに参加することは、確実に社会貢献性への関心をアピールできます。また、チームワークやリーダーシップ、コミュニケーション能力につながるエピソードにも困らないジャンルなのではないでしょうか。
3.資格取得
これは、合格しないと実績にならない分、若干リスクの高い戦略になりますが、目に見える成果としては最もわかりやすい実績です。また、誰でも取得できる資格だとアピールにならない可能性もあるため、難易度と期間を天秤にかけ、半年間で取得可能な資格をリサーチし戦略を立てることが大切です。例えば、IT系資格や語学試験、ビジネススキルに関する資格など、資格取得を通じて、自分の専門性や継続的な学びへの意欲をアピールしましょう。
4.自主プロジェクトの立ち上げ
一ヶ月で作れるテーマとしても紹介しましたが、半年間時間をかけることでより経験と学びを得ることができるはずです。ブログや起業、イベント、サービス開発など、ほとんどの大学生が経験していない挑戦をすることで、他の学生の4年間分の行動を取り返せるチャンスがあります。
自分の興味や関心に基づいた小さなプロジェクトを立ち上げ、真剣に取り組むことで、面接で誇れる経験になります。例えば、ブログを書いたり、イベントの企画集客開催、オンラインビジネスを企画するなど、自分のアイデアやスキルを活かしながらプロジェクトを遂行してみましょう。
5.クラブやサークルの活動
クラブやサークルに参加している方は、あらためてクラブやサークルの活動に向き合い、力を入れて行動してみるのも良いでしょう。半年間クラブやサークルの活動に真摯に参加し、組織運営やイベント企画などのリーダーシップ経験を積みましょう。面接では、その活動を通じて得たスキルやチームワークをアピールできます。
6.独学でプログラミングスキルの習得
半年間時間があり、ITコンサルやSEなどの業界に興味があるのであれば、半年間で独学やオンライン学習を通じてプログラミングスキルを習得してみましょう。面接では、自己学習能力や技術スキルをアピールできますし、実務においても必ず重宝します。
また、先ほど挙げた業種でなくても、あらゆる企業で求められている汎用的なスキルになりつつあるため、挑戦しておくと選択肢が広がる可能性が高いです。
7.海外での語学研修や留学
留学も、お金がかかるというデメリットはありますが、面接においてわかりやすい実績になります、半年間の語学研修や留学を経験することで、異文化コミュニケーション能力や語学力、柔軟な思考力を身につけることができ、視野が広がります。実際、筆者の知人も海外に興味がなかったが、就職留年をきっかけに留学し、海外事業に携わりたいと将来のビジョンを掲げたという人もいます。